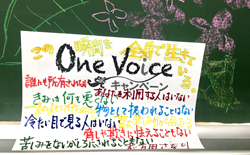4月16日(水)、日本でデジタル性暴力の被害者支援に取り組む団体「NPO法人ぱっぷす」のメンバーとともに、韓国・ソウルにある「韓国サイバー性暴力対応センター」を訪問しました。

(韓国サイバー性暴力対応センターの皆さまと)
このセンターは、インターネット上で発生する性暴力やデジタル性犯罪に対処する専門機関として、2007年から活動を続けており、以下のような幅広い支援と取り組みを行っています。
- 被害者支援と相談対応
- 違法コンテンツの削除支援
- 啓発活動と教育
- 政策提言と制度改善
これまでに約1100人の被害者を支援し、同意のない画像流布の禁止を訴えるなど、法的・心理的なサポートを行っています。特筆すべきは、政府からの補助金に頼らず、草の根の活動として支援を継続している点です。相談は主にインターネット検索や警察、全国共通の相談番号「1344」などを通じて寄せられており、20~30代の若い女性の利用が多くなっています。
訪問時には、韓国におけるデジタル性暴力関連法の変遷や、現場での実務的な課題についても説明を受けました。たとえば、韓国では「撮影時の同意」と「流布時の同意」が別々に定義されており、流布時に同意がなければ処罰の対象となります。一方で、SNSでの嫌がらせコメントや、性的でない画像の悪用など、現行法では対応しきれないケースも多く、法整備のさらなる強化が求められている現状も共有されました。
意見交換では、日本と韓国における公訴時効の違いが議論になりました。韓国では流布罪の公訴時効は7年、営利目的の場合は10年とされているのに対し、日本は3年と短く、被害者が気づいた時には既に時効が過ぎているケースも多いのが現状です。そのため、日本では加害者の処罰よりも、画像の削除を中心とした支援が主流となっています。こうした点からも、日本の制度上の課題が浮き彫りになりました。
(ミーティングの様子)
近年、AIやインターネット技術の急速な発展により、デジタル性犯罪は増加の一途をたどっています。しかし、多くの国で法整備が追いついていないのが現状です。今回の視察を通じて、韓国サイバー性暴力対応センターのような民間の専門機関の存在がいかに重要かを改めて実感しました。
このセンターは、デジタル性暴力を「個人の問題」ではなく、「社会構造によって生じる暴力」として捉え、被害者と共に問題を言語化し、社会に伝えていくことを大切にしています。活動家たちの姿勢や実践は、私たちにとって大きな学びとなりました。
今後、日本においても制度・支援体制・教育のすべての面から、被害者中心のアプローチを進めていく必要があると強く感じました。
韓国サイバー性暴力対応センターの皆さん、ありがとうございました!
|
<韓国視察の概要> 2025年4月13日〜16日、Springスタッフ・NPO法人ぱっぷす・メディア関係者3名とともに、韓国:ソウルへ現地視察に行きました。 本視察は、同じ文化的背景を持つ東アジア圏の性犯罪規定(刑法および特別法)の法整備や運用に関する調査・研究を行い、現行の日本の刑法性犯罪規定および性犯罪に関する特別法に内在する課題を明らかにすることを目的としています。
①公訴時効撤廃、停止・延長についての意見交換 (順次、各訪問箇所の報告記事を掲載しています)
また、今後下記を予定していますので、お楽しみに。
|
<関連記事>
【韓国視察報告1】タクティンネイルを訪問しました
【韓国視察報告2】 アハ!青少年性文化センターを訪問しました
【韓国視察報告3】韓国性暴力相談所を訪問しました
【韓国視察報告4】法律家と性犯罪・公訴時効に関する懇談会をしました
【韓国視察報告5】韓国「国会討論会」に登壇し、記者会見を実施・取材を受けました【メディア掲載】
※本視察・イベント開催・白書発行は、JSPN/ジョイセフの支援をうけて実施しました。
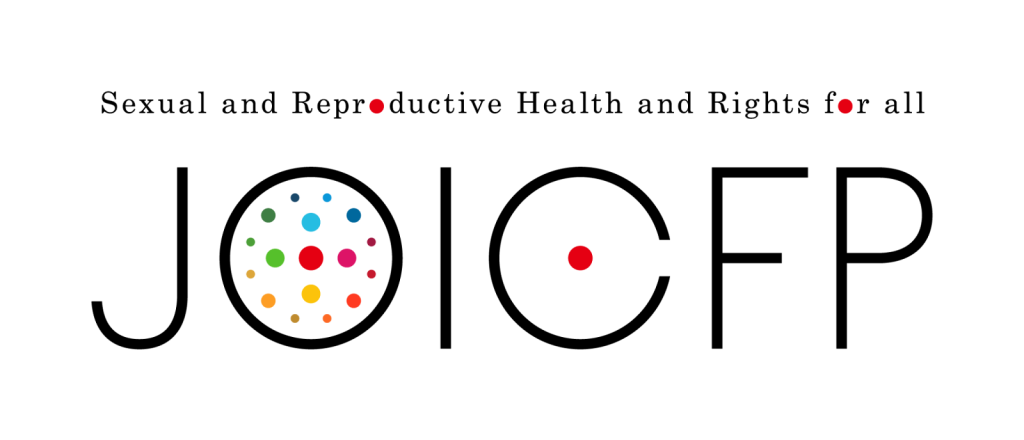

.png)